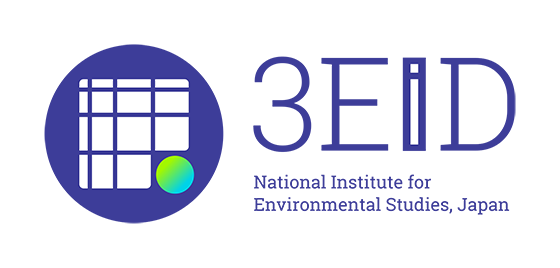よくある質問
これまで3EIDの利用者の方からの質問の中で,頻度が高かったものを,回答とともにまとめました。今後とも,共通性の高そうな質問とその回答をこのページに追加していく計画ですが,いただいたご質問に対して,個別に回答することができない場合があることをご了承下さい。公的研究機関としての限られたリソースから,公益性の高いものを除き,個々のLCA事例のコンサルティングにあたるものにつきましては対応が出来ないことをご了解ください。
- 3EIDを用いて製品Aの生産に伴う排出量を計算するにはどうすればいいですか?
-
3EIDの原単位に製品Aの金額(何百万円分か)を乗じてください。
対象とする製品や素材に該当する3EIDの部門を選びます。そして,その製品や素材の金額(何百万円分あるか)をその部門の原単位(排出量/百万円に掛けることで,その製品や素材の一連の生産プロセスにおける排出量を簡単に計算することができます。これは,LCAの産業連関分析法(IO-LCA)と呼ばれるインベントリ分析の方法です。IO-LCAの利点として以下の点が上げられます。- 原単位があれば,計算が簡単で手間がかからない。
- どの段階からどの段階までの生産プロセスを考慮した排出量であるか(システム境界)が明確。
- 平均的な製品や素材の排出量が計算できる(同じ製品でもメーカーやグレードによって様々ですが,IO-LCAではそれらの平均的な排出量を計算)
- 広告や金融,行政サービスなど,積み上げ法では把握しにくい部門からの排出量も含まれる。
しかしながら,以下のような弱点もあります。
- 個々の製品の生産過程の特徴を反映した排出量が計算されない(あくまで平均的な製品の排出量(利点でもありますが))。
- 一つの部門に該当する商品やサービスは複数存在することが多く,原単位はそうした多種の製品の平均的な単位生産額あたりの排出量を示す。
- 原単位が提供されていない環境負荷の計算はできない(自分で原単位を作成すればいいのですが,約400もの部門の環境負荷量を推計する必要があり容易ではない)。
他の利点や問題点もありますが,それらについては市販のLCAの解説書等をご参考ください。
上記のIO-LCAの強みを生かして,弱みをカバーするLCAの方法として積み上げ法を併用するハイブリッド法(Hybrid-LCA)があります。Hybrid-LCAは,積み上げ法で評価対象の生産プロセスの特徴を反映したインベントリデータを作成し,積み上げ法で得られなかったプロセスから出る排出量をIO-LCAを利用して算出する方法です。LCAの目的とLCAに掛けられるコストによりますが,自社の製品の生産プロセスの特徴(環境対策を取っているなど)を反映して,製品の生産に関連する排出量を包括的に計算したい場合は,このHybrid-LCAをお勧めします。3EIDのデータはHybrid-LCAへの利用も可能です。
Hybrid-LCAの詳しい解説についてお知りになりたい場合は,市販のLCAの書籍等をご活用下さい。
- 製品Aにはどの部門の原単位を使えばいいですか?
-
産業連関表には各部門の定義・範囲,品目例示,注意点等が記述されていますので,それらも評価対象の該当部門を選定する場合の参考になります。産業連関表の付帯表である「部門別品目別国内生産額表」が総務省から公表されています。この表には産業連関表の各部門に該当する製品の種類がより詳細に示されています。また,産業連関表の部門と貿易統計の輸出品コードとの対応表も参考になります。
- CO2排出原単位の「t-CO2」と「t-C」はどう違うのですか?
-
「t-CO2」はCO2としての質量を示しますが,「t-C」はCO2の炭素分だけの質量を表します。
つまり,「t-CO2」=[(44: CO2の分子量)/(12: 炭素の分子量)]×「t-C」の関係です。
日本の公式な温室効果ガスインベントリは,排出量を「t-CO2」で表記していますので,CO2排出量を示すには「t-CO2」が一般的と考えられます。一方,「t-C」は,CO2にはなっていないが,プラスチックや化学製品として消費された炭素量にも着目した分析(炭素バランスの確認など)を行う場合には,CO2として大気へ放出された炭素量と加算できる利点があります。
- 「物量表」というのが推計に利用されていますが,3EIDには「物量表」は入っていますか?
-
入っておりません。
「物量表」は産業連関表の付帯表ですので,ご覧になりたい方は産業連関表をご覧下さい。ただし2020年表からは物量表が廃止されました。
- 原単位の部門名についている「★」マークは何を意味するのですか?
また,「★」マークが1つの場合と2つの場合とがありますが,それぞれどういった違いがありますか? -
★マークは産業連関表における生産活動主体分類の注釈記号で,以下の区分を示します。
- ★★:政府サービス生産者(例:政府機関,特殊法人)
- ★ :対家計民間非営利サービス生産者(例:宗教団体,労働組合,学術・文化団体,政治団体)
- 無印:産業
- 各部門の年間電力使用量(kWh/年)は3EIDには書かれていますか?
-
部門別の年間電力消費量は,産業連関表に付帯の「物量表」には掲載されています。「物量表」には事業用電力と自家発電に分けて,部門別の年間電力使用量(百万kWh/年)が書かれていますので参照して下さい。しかし,2020年表から「物量表」が廃止されたため,2020年版の3EIDには独自に推計した部門別電力消費量(GJ/年)を掲載しています。
- 原単位には「(I-A)-1型」と「(I-Ad)-1型」の2つの数字がありますが意味もしくは違いは何ですか?
-
例えば,CO2排出原単位の「(I-A)-1」型と「(I-Ad)-1」型の違いは,部門の生産活動に要した輸入品に関するCO2排出量を「含む」か「含まない」かの違いです。前者は輸入品の生産に伴うCO2排出量を,国産品と同じ排出量であると(同じ技術で生産されたと)仮定して計算し,輸入品の生産による排出量も国産品の生産よる排出量も含めた値を示します。一方,後者は輸入品に関するCO2排出量は含まず,国産品の排出量のみを計算した値を示します。
前者の原単位は,ある製品や素材の生産プロセスで発生したCO2排出量を,輸入品の生産段階も含めて,すなわち国内外を問わず発生するCO2を包括的に計算する場合に適しています。しかし,「国産品と輸入品が同じ技術で作られる」ことを仮定しているため,国産品と輸入品の生産技術が実際は大きく違う場合,かつ,輸入品の流通シェアが高い製品については,該当する原単位の示す排出量は実態と異なったものになります。例をあげると,国内生産のほとんどなく,その採掘方法や技術も大きく異なると考えられる原油や石炭,アルミなどの部門が該当します。また,産業連関分析は波及計算のため,こうした製品を原料とする部門の原単位(石油製品,石炭製品,アルミ圧延製品など)も,その影響を少なからず受けます。製品や素材からの包括的な排出量を計算できる利点はありますが,結果を解釈する場合は,こうした大きな仮定を設けて計算していることにご留意ください。
後者の原単位は,日本国内(正確には産業連関表の国内概念の範囲)で排出されるCO2排出量のみを計算する場合に適します。また,輸入品に関する排出量を別途計算し,国産品からの排出量と加算することで,より実態に近い排出量を計算する場合にも活用できます。二つの原単位の特長を踏まえ,評価や分析の目的に応じてどちらの原単位を用いるかを検討してください。
- 例えば金属製品の場合,その材料となる金属の採掘などに伴う排出量も原単位には含まれますか?
-
はい,理論的には含まれています。
3EIDの原単位は産業連関分析に基づいていますので,理論的は国内の全ての生産活動を考慮して計算した値になっています。そのため,金属の採掘に伴う排出量も各部門の原単位に含まれています。
しかし,現在は金属の採掘は国内ではほとんど行われていないため,上記Q8で説明した理由により,二種類の原単位の示す値は実質的にはそれぞれ次のようになっています。「(I-A)-1」型の原単位の場合,輸入品を国産品の生産技術と同様と仮定して排出量を計算しています。つまり,鉱石や地金の形で輸入された金属の採掘に伴う排出量は,国内での金属の採掘から発生した排出量と同量と見なしています。国内と国外の採掘技術やプロセスが異なること,国内への供給の多くが輸入品である金属の実態を踏まえると,国内の採掘を基にした排出量を輸入品にも当てはめて計算した原単位は,実態との乖離が大きいことが懸念されます。したがって,理論的には金属の採掘時の排出量は含まれていると言えますが,その数値の解釈には計算の前提条件をご理解いただきますようお願いします。
一方, 「(I-Ad)-1」型の原単位の場合,輸入品に関する排出量は除かれ,国産品の排出量のみが含まれます。そのため,国内における採掘時の排出量が原単位に含まれます。ただし,金属の大部分を輸入していることから,金属製品関連部門の原単位に対する国内の採掘時の排出量の影響は大変小さいものとなっています。
- 百万円あたりの排出量を原単位として提示していますが,3EIDには1tあたりや1m3あたりといった物量単位の排出量を示す原単位はありますか?
-
ございません。しかし,3EIDの原単位を使って簡易に計算することができます。
評価したい製品や素材の単価(百万円/t)や(百万円/m3)を調べていただき,下式のように,その製品と対応する部門の原単位に乗じて下さい。3EIDの金額あたりの原単位を物量あたりの原単位に単位を変換することができます。このとき,3EIDの原単位が百万円あたりであるため,単価は百万円単位で設定することに注意してください。3EIDの原単位(排出量/百万円)×単価(百万円/t)=物量あたりの原単位(排出量/t)
この方法で求めた物量あたりの原単位を用いる場合,次の点に注意することが必要です。この方法で原単位の単位を変換すると,同じ部門の原単位に該当する商品(複数)は全て,「単価に比例して物量あたりの生産に伴う排出量も大きくなる」こと仮定したことになります。つまり,同じ部門に該当する製品がAとBあり,Aの単価がBの2倍であれば,Aの生産に伴う排出量もBの2倍大きいとなります。
例えば,具体的には「電池」部門には,マンガン電池,アルカリマンガン電池,リチウム電池,鉛電池,アルカリ電池,リチウム・イオン電池など多種の商品が該当します。実際には,これらは材料も生産方法も異なるため,単価に比例して物量あたりの排出量が大きくなる訳ではありません。しかし,3EIDの原単位から単価を用いて物量あたりの原単位を計算した場合,各電池の生産に伴う単位物量あたりの排出量は単価に比例した数値になります。
- 原単位には製品の使用時に発生する排出量は含まれますか?
-
いいえ,含まれておりません。
例えば「乗用車」部門の原単位(生産者価格ベース)には,乗用車の生産に伴う排出量は含まれていますが,購入後,走行時に発生する排出量は含まれていませんので,必要な場合は別途積み上げ法で計算する必要があります。3EIDには,化石燃料の発熱量とCO2排出係数が含まれています。走行時にガソリンや軽油の燃焼により発生するCO2の量を計算する場合に活用することができます。さらに,その走行で消費したガソリンや軽油の生産に伴い発生したCO2等を計算する場合には,「石油製品」部門の原単位を利用することができます。「石油製品」部門の原単位は,重油やガソリン等の石油製品の生産に伴う排出量を示しており,その燃焼により発生する排出量は含まれておりません。同様に,エアコンやパソコンが該当する部門の原単位も生産に伴う排出量を示しています。使用時の電力消費に伴う排出量を求める場合は,「電力」部門の原単位を使って計算することができます。
なお,温室効果ガス全般に関する排出係数等の情報については,当所の温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)のホームページもご参照ください。
- 原単位には生産設備の建設など,固定資本形成に伴う排出量は含まれますか?
-
いいえ,含まれておりません。
産業連関表では,通常の生産(内生部門)に要した製品や材料と,固定資本形成(外生部門)に要した製品や材料とを区分して記述しています。3EIDの原単位は,内生部門の間の製品の投入構造を基に原単位の計算を行っています。つまり,原単位には通常の生産プロセスからの排出量だけが含まれています。しかし,3EIDの原単位と産業連関表の数値を使って,年間のどの固定資本形成に伴って,どれほどの排出があったを計算することができます。産業連関表の付帯表に「固定資本マトリックス」があります。この付帯表から,どのような固定資本形成に対して,産業連関表の各部門から年間で何百万円の投入があったかを知ることができます。この金額を各部門の原単位に乗じることによって,その年の固定資本形成に伴う排出量を求めることもできます。固定資本形成の定義については,産業連関表に詳細な解説があります。入手可能な方はそちらをご覧ください。産業連関表では基本的に,耐用年数が1年以上で購入者価格の単価が10万円以上の建設物,機械,装置等の再生産可能な資本財の取引額,並びに資本用役を提供する家畜及び果樹等の成長増加を固定資本形成としています。